神経系の3ステップ(入力・情報のまとめ処理・出力)から読み解くバランスのしくみ
「筋力もあるのにふらつく…」その違和感、放っておくと危険かもしれません
・歩いているとフラッとする
・フラフラして歩いていると言われるが自覚が無い
・真っすぐ歩いているつもりなのに、気づいたら斜めに進んでいる
・最近、よくつまずくようになった
そんな症状が気になっても、
「年齢のせいかな」
「疲れているだけかも」
と放置してしまう方が多くいらっしゃいます。
ですが、その“ふらつき”、神経のセンサーのズレが進行しているサインかもしれません。
悪化すると、転倒やケガ、外出が怖くなるといった日常生活への影響も避けられなくなります。
当院では、脳神経系の基本機能「入力・情報のまとめ処理・出力」という視点から、 歩行時のふらつきの根本原因を見極め、一人ひとりに合った改善プランをご提案しています。
神経のセンサーはなぜズレるのか?
バランスを保つための“神経のセンサー”は、日々の生活習慣やストレスによっても乱れやすくなります。
例えば
- 長時間のスマホやパソコンで視線が固定される
- 姿勢が崩れ、首や背中が緊張し続ける
- 運動不足で関節や筋肉からの感覚入力が減る
- 睡眠不足や精神的ストレスが脳の処理能力を低下させる
こうした要因が積み重なると、「視覚」「バランス感覚(前庭感覚)」「深部感覚(関節や皮膚)」といった 感覚センサーが正しく働かなくなります。、
その結果、脳が受け取る情報に誤差が生じる=ズレるという現象が起こります。
このズレた情報のまま体を動かすと、脳は間違った判断をし、不安定な姿勢やふらつきが起きてしまうのです。
バランスは脳の「3つの働き」で保たれている
私たちがスムーズに歩いたり、まっすぐ立ったりできるのは、脳が常に働いているおかげです。
その働きは、大きく「脳の役割」を3ステップに分けることができます。
ステップ①「入力」
まず最初に行われるのが「入力」のステップです。
これは、身体の中にある“センサー”たちが「今の自分の状態」や「周囲の状況」を感じ取り、脳に情報を送る役割を果たします。
たとえば
- 目(視覚)は、周囲の景色や地面の傾き、水平等の情報を脳に送る
- バランス感覚(前庭感覚)は、頭の動きや加速、傾きなどのバランス情報を脳に送る
- 関節・筋肉・足裏など(深部感覚)は、体が今どんな姿勢をしていて、どこに体重が乗っている等の情報を脳に送る
これらの感覚が正しく入力されることで、
脳は「自分は今、どこにいて、どんな姿勢で、どの方向に動いているのか?」を知ることができます。
しかし、長時間同じ姿勢をとっていたり、疲労やストレスが重なったりすると、 これらのセンサーが鈍くなったり、ズレた情報を送ってしまうことがあります。
たとえば、目が疲れてピントが合いにくくなると、地面の傾きや距離感を正確に捉えられなくなったり、 足裏の感覚が鈍ると、体重がどちらにかかっているのかがわからなくなったりします。
つまり「入力」の段階で情報がズレてしまうと、その後の処理(まとめ・判断)にも大きく影響し、 結果としてふらつきや不安定な動作につながってしまうのです。
ステップ②「情報のまとめ処理」
体のいろいろな部分から集められた感覚情報(目で見た景色、耳で感じる揺れ、足裏で感じる地面の傾きなど)は、 そのままではバラバラで使えません。
これらをひとつに整理して「今、自分の体がどんな状態にあるのか?」を脳で判断する作業が「情報のまとめ処理」です。
- 目では「地面は平らに見えている」
- 耳の中(前庭)では「少し傾いている」と感じている
- 足の感覚では「体重が片側に乗っている」と伝えている
このように感覚が食い違っていると、脳は「今の身体の状態」を正確に把握できず、間違った判断をしてしまいます。
つまりこのまとめ処理がうまくいかないと、「まっすぐ立っているつもりなのに実際は傾いている」 「自分では正しい方向に歩いているつもりなのに片側に流れてしまう」といったことが起こります。
ふらつきや姿勢の不安定さは、こうした感覚の食い違いが原因になっていることがとても多いのです。
ステップ③「出力」
「入力」された感覚情報が脳でうまく整理(情報のまとめ処理)されたら、次はいよいよ「出力」の段階です。
ここでは、脳が「この状況なら、こう動くのが正しい」と判断し、その命令を体の各部に伝える作業が行われます。 つまり「どの筋肉を、どのタイミングで、どれくらいの力で動かすか?」を指示しているのがこのステップです。
たとえば
- 階段を上がるときに、体が前に倒れすぎないようにバランスを取る
- 段差につまずきそうになった時に、とっさに足を出して体を支える
- 混雑した駅で、前から人が来ても自然に避けて歩ける
これらの動きはすべて「出力=脳からの指令」によって成り立っています。
しかし、「入力」や「情報のまとめ処理」がズレていると、正しい判断ができないため、 「今、必要な動きとは違う指令」を出してしまうことがあります。
その結果
- 足を出すタイミングがズレて、よろけてしまう
- バランスを取るために無駄な力が入り、体がガチガチになる
- 左右どちらかに傾いて歩いてしまう
といったふらつきや不自然な動きが起きるのです。
つまり「出力」エラーとは、「動かし方のズレ」。
それは筋肉の問題ではなく、「いつ・どう動かすか」の神経の指令が狂っていることが原因なのです。
気づかないうちに進行するふらつきの兆候
以下のような症状は、感覚入力や脳の処理の乱れが進行してい可能性があります。
- 買い物中、人混みの中を歩くのが怖くなってきた
- 駅の階段や段差でバランスを崩しそうになる
- 片足立ちで靴下が履けない、ふらついてしまう
- 玄関で靴を履くときにふとよろける
- 歩いていても足元がふわふわしたように感じる
- 病院では「異常なし」と言われたけど、やっぱり不安定
こうした症状がある方の多くは、「今すぐ困っているわけじゃないけれど、なんとなく不安」という段階です。
しかし、この状態を放っておくと、転倒や外出の制限、運動への苦手意識などにつながってしまいます。
改善のステップ|感覚から「無意識でも安定して動ける身体」へ
ふらつきを改善するためには、「筋肉を鍛える」のではなく、 まずは「正しい感覚を脳に届ける」ことが大切です。
そのうえで、脳が情報をうまくまとめ、自然に体が反応できる状態を目指していきます。
イメージとしては、バラバラだった信号が整理されて、 必要なタイミングでブレーキやアクセルが正しく働く自動運転のような体の状態です。
感覚を正しく届けるための土台づくり
- 目の動きと姿勢の連動を整える「視線トレーニング」
- 頭の位置と体幹のバランスを取る「前庭系刺激」
- 足裏等の関節からの感覚を鍛える「感覚刺激トレーニング」
体の反応を自動で安定させるトレーニング
- 頭・体幹・脚を協調させる「連動エクササイズ」
- 姿勢と目線を安定させる「協調トレーニング」
- 入ってきた感覚に対して、無理なく正確な動作ができる状態を再学習
このように「感じて→まとめて→動く」までの流れを神経から整えていきます。
こうしたアプローチにより、無意識でも姿勢が安定していきます。
その結果、「歩いているときにふらつくのでは…」という不安も解消されていきます。
実際にふらつきが改善したケース
では、実際に神経学トレーニングでふらつきが改善したケースを紹介します。
60代女性|長年のふらつきと外出不安
長年「歩くとフラフラする」「まっすぐ歩けていない気がする」というふらつき。
病院でMRI等の検査を受けたものの「異常なし」と言われた60代の女性。
運動も取り入れても改善せず、徐々に買い物や散歩に出かけるのも不安になり来院されました。
当院では検査した結果
- 視線と体幹の協調
- バランス機能
が弱い。
そのため施術と神経学トレーニングを週1回のペースで行い、
- 視線安定エクササイズ
- 体幹回旋と頭部位置の協調訓練
3ヶ月後には、「駅の階段も怖くなくなった」「外出に対する不安が減った」と満足されました。
現在は再発予防に月1回来院されています。
よくある質問(FAQ)
Q. 軽いふらつき程度でも通って良いですか?
はい。
小さなズレこそ、将来の転倒リスクにつながるサインです。
違和感の段階で神経を整えることで、 大きな不調を未然に防ぐことができます。
Q. 神経のセンサーは年齢とともに悪くなりますか?
確かに年齢とともに感覚は鈍くなります。
ただし、何歳からでも再教育(再学習)できます。
70代・80代の方でも改善スピードは遅くなりますが改善可能です。
薬やマッサージとの違いは何ですか?
投薬やマッサージは一時的な対症療法です。
当院の神経学トレーニングは、 根本的に「身体の安定機能」を修正するアプローチです。
ふらつきは病院の検査が先
ふらつきは、神経のズレだけでなく、脳の病気等の重大な疾患が隠れていることもあります。
当院での施術を受けていただく前に、必ず一度、病院(整形外科等)での診察を受けて、 重大な病気が無いことを確認してください。
万が一、病気が見つかった場合は、その治療が最優先となります。
「病院で異常が見つからなかったけれど、ふらつきが続く」
「原因がはっきりしない不安定感がある」
そんな方には、当院の神経の働きに着目したアプローチが有効なケースがあります。
ふらつきのお悩みはご相談ください
ふらつきは「少し気になる」段階のうちに対処することが何より大切です。
当院では、神経の働きに着目して、あなたの身体の状態に合わせた神経再教育を行っています。
・ふらついて転ぶことがある
・まだ転んだことはないけれど怖い
・このままだと不安
そんな想いを感じている方は、ぜひ一度当院にご相談ください。
あなたの「不安定感」を、安定へと変えていきましょう。
この記事に関する関連記事
- ゴルフの捻転不足の原因は胸椎と股関節だった!?腰を回すときの本当の動きとは
- 「腰痛の原因」腰が回らない本当の理由は胸椎と股関節にあった!
- 腰痛の原因!? 知っておきたい腸腰筋のメカニズムと神経ストレッチ(大腿神経)
- 股関節痛改善は筋肉のストレッチより神経ストレッチ(大腿神経)
- 手根管症候群を原因から改善する神経ストレッチ(正中神経)
- 手のひらのしびれ・痛みを改善する神経ストレッチ(正中神経)
- 肩・首痛い時に効果的な神経ストレッチ(副神経)
- 手のしびれ・痛み(橈骨神経麻痺)改善の神経ストレッチ(橈骨神経・後骨間神経)
- 【自律神経失調症】自律神経とストレスの関係
- 手のしびれ・痛み(ギヨン管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)
- 自律神経失調症への整体の効果:不眠・めまい・倦怠感等
- 小指のしびれ(肘部管症候群)改善の神経ストレッチ(尺骨神経)
- うつ病の人がとる行動をパターン別に説明
- 前腕外側の痛み・しびれ改善の神経ストレッチ(筋皮・前腕外側皮神経)
- 腓骨神経麻痺の症状・原因と神経ストレッチ(総腓骨神経)
- 自律神経失調症による発熱の原因と対処法
- うつ病の種類を原因・症状・病型ごとにわかりやすく説明
- うつ病で身体の痛みが起こる理由をわかりやすく解説
- 【外側大腿皮神経痛の改善方法】太もも外側の痛み・しびれ改善に効果的な外側大腿皮神経ストレッチ
- 坐骨神経痛の原因を深く解説
- 椎間板ヘルニアの痛み・しびれの原因は脳・神経にある
- 椎間板ヘルニアには種類がある?椎間板ヘルニアの種類を解説
- 催眠療法(ヒプノセラピー)での催眠状態ってどんな状態?
- 運動療法で痛み・シビレを脳・神経から改善するコツ
- 腰の痛みと姿勢の悪さは関係無し 腰の痛み改善に大事な考え方
- ツライ腰痛も簡単な腰痛体操で症状軽減
- 腰痛の原因は脳にある!脳神経学視点から腰痛の原因を解説
- 催眠療法(ヒプノセラピー)の受け方のコツは安心と信頼
- 治らない野球肩改善の神経ストレッチとクワドリラテラルスペース(腋窩神経)
- 大人の起立性調節障害の症状や仕事への向き合い方
- 潜在意識・顕在意識と催眠療法(ヒプノセラピー)の関係
- 催眠療法(ヒプノセラピー)がトラウマ解消に効果的
- 催眠療法(ヒプノセラピー)は怪しい?催眠療法の疑問を解消
- テニス肘を放置して悪化すると手術が必要になることも!
- テニス肘の原因を解説!日常生活で出来る予防
- 坐骨神経痛の症状は主に4種類
- テニス肘の原因を筋肉・動作等からわかりやすく説明
- グロインペイン症候群を改善する神経ストレッチ(閉鎖神経)
- ロキソニンが効かない腰痛の改善方法
- 膝内側の痛み(ハンター管症候群)の改善に神経ストレッチ(伏在神経)
- プラシーボ(プラセボ)効果とは?/整体の効果は思い込み?
- めまいの種類/回転性・末梢性・メニエル病のめまいって何?
- 神経を伸ばす神経ストレッチの目的と役割
- 慢性痛の原因は脳の記憶!慢性痛の改善方法も紹介
- 三叉神経痛・顔面神経痛の原因と神経ストレッチ(三叉神経)
- アキレス腱炎に効果的な神経ストレッチ(腓腹神経)
- 頚椎症性神経根症の「症状」「「似た症状」「神経根」とは?
- 重症な足底筋膜炎にも効果的な神経ストレッチ(脛骨神経)
- 猫背改善にストレッチ・筋トレより効果的な神経学トレーニング
- 自律神経失調症と脳・神経学の関係
- ペンフィールドのホムンクルス(脳地図)をセルフケアに応用する考え方
- ボディマッピングと脳の予測
- オスグッド改善後の再発予防
- 脳内の身体の地図 (ボディマップ)と整体(ボディマッピング)の関係
- 整体後の好転反応とは?
- 横隔膜の硬さと自律神経・首の関係
- 足底筋膜炎と足底腱膜炎の違い
- 腰や首の牽引療法は効果がない
- 「整体は意味ない」と言われる理由
- シーバー病が改善しても身長伸びる!
- 気象病・天気痛の原因と改善する考え方
- ベアフットシューズの効果で様々な症状を改善
- 重症なオスグッド改善の動かしストレッチ
- 産後の骨盤矯正は本当に必要?
- 骨盤矯正ダイエットで痩せるのは本当?
- 「椎間板が潰れている」「背骨のスキマ狭い」とは?
- 椎間板ヘルニアは手術後64%再発する
- 椎間板ヘルニアがレントゲンでわからない理由
- オスグッド病が改善しても身長伸びる!
- オスグッド病と他のスポーツ障害との見分け方
- 骨盤・背骨等の身体の歪みは気にしなくて大丈夫
- 側弯症改善に三半規管トレーニング
- オスグッドで多い質問
- オスグッドと成長痛の違い
- 坐骨神経痛はマッサージでは改善しない
- 坐骨神経痛の施術は整骨院でも可能?
- 坐骨神経痛は病名ではない!?
- 坐骨神経痛の痛み・しびれ部分が人により違う理由とは?
- 腰痛は揉んでも改善しない
- オスグッド病にストレッチ不要
- オスグッドにアイシングはNG


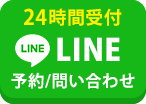
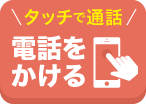





お電話ありがとうございます、
大阪・高槻スポーツ整体 ぎの整体院でございます。